 「映画撮影の経験から」
「映画撮影の経験から」2025年度 新歓ブログリレー #4
 「映画撮影の経験から」
「映画撮影の経験から」
 「映画撮影の経験から」
「映画撮影の経験から」 映研副部長の佐藤です。今回のブログリレーでは、『ブレット・トレイン』という映画を紹介させていただきます。2022年公開のアクション映画で、主演はブラッド・ピット、監督は『ジョン・ウィック』『デッドプール2』のデビッド・リーチです。
映研副部長の佐藤です。今回のブログリレーでは、『ブレット・トレイン』という映画を紹介させていただきます。2022年公開のアクション映画で、主演はブラッド・ピット、監督は『ジョン・ウィック』『デッドプール2』のデビッド・リーチです。
舞台は日本の新幹線(=bullet train)。主人公の「レディバグ」は悪運を呼び寄せる体質で、何の依頼をこなすにしてもどこかうまくいかない。とある人物の代理として依頼を引き受け、東京発京都行の新幹線に乗り込むのですが、そこで複数の殺し屋と遭遇してしまい、大きな陰謀に巻き込まれていきます。日本の新幹線は、定刻通りに駅に到着して客が乗り降りしますが、その時以外は下車できない、いわば半密室。また前後に車両が連なっているため逃げ隠れも困難。そこで繰り広げられる、コメディ要素たっぷりな殺し屋たちの駆け引きから目が離せません。
以下ネタバレを含む可能性があるのでご留意ください。レディバグが遭遇する殺し屋も個性豊かです。あらゆる人間をきかんしゃトーマスに喩える「レモン」と、それを諌める「タンジェリン」の二人組の殺し屋の掛け合いはクスッとします。とある目的で新幹線に乗り込んでいる性悪少女の「プリンス」と、彼女を狙う「木村」など、彼らの起こした行動が意外なところでつながり、衝突を起こし、時に呉越同舟し、クライマックス・京都駅に向かって収束していきます。物語序盤から登場していたとある物が、紆余曲折を経て最後にスポットライトを浴びるのは「えーっ!? それが!?」となること間違いなし。
アクションシーンも魅力の一つ。レディバグは平和的解決を望むため銃は使わないのですが、殺し屋は容赦なく襲い掛かってくる。その場にある道具を使ったり相手の武器を利用したり、あるいは乗客・乗務員に目立たぬよう戦闘をごまかしたりと、緩急のきいた小気味のいいアクションが楽しめます。また、真田広之演じる「長老」の刀を使った殺陣も見られます。
前述したように舞台は日本なのですが、その日本の描写が突っ込みどころ満載で、逆に面白みになっています。例を挙げるとすれば、日本のアニメかあるいはゆるキャラを意識したであろう「モモもん」というキャラクターや、挿入歌として流れる「ヒーロー」「上を向いて歩こう」、夜に東京を発って朝に京都に着く新幹線、名古屋駅を過ぎたころに見えてくる富士山、謎に再現度の高い米原駅、やたら歴史的な京都、いかにもなヤクザなど、枚挙にいとまがありません。このような”トンチキ日本”が好きな方、これを読んでいる方にもいるのではないでしょうか。
この作品、実は伊坂幸太郎の『マリアビートル』という小説が原作となっています。この映画は東京から京都に向かうのですが、小説では盛岡に向かう新幹線が舞台となっています。またこの映画は、終盤にかけて脚色が強くなり、とても”ハリウッド的”といったようなスケールの大きい事件に発展していきます。新幹線という密室での殺し屋たちの物語を組み立てた伊坂幸太郎の巧さと、それをトンチキに仕上げた映画スタッフの違いも面白いところ。「この映画が気に入った!」という方は、こちらの本も読んでみてこの映画と比較すると楽しいかもしれません。
以上、映画『ブレット・トレイン』について紹介しました。私はトンチキな映画が大好きなので、そんな映画を知っているという方がいましたらぜひともこのサークルに入っていただき、紹介してほしいなと思います。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。

映画撮影イメージ
他にもおすすめしたい映画はあるのですが、
映画のことを全く知らなくとも、


法学部三年の田仲です。
恒例のブログリレーが今年も始まります。これは部員が一人一本ずつ、映画に関する記事を書いていくという企画です。慣習に則り、初回は当代の部長である私の記事から始めていこうと思います。今回は私が敬愛する監督、クロエ・ジャオについてです。
クロエ・ジャオは、二〇一五年に長編デビューを果たした、比較的若い監督です。現在の監督作品は日本未公開の「Songs My Brother Taught Me」、「ザ・ライダー」、「ノマドランド」、そして「エターナルズ」の四作品で、そのうち「ノマドランド」は金獅子賞とアカデミー作品賞を受賞しています。私は「ノマドランド」でクロエ・ジャオを知り、以来彼女のファンなのですが、今回は彼女の映画の特色と魅力について私見を述べさせていただこうと思います。
クロエ・ジャオの色というのは、彼女独自のリアリズムにあると私は考えます。これはストーリー面と映像面の二つに大別できます。まずはストーリー面についてですが、彼女の描く物語には極めて大きな特徴があります。それはキャラクターの多くが実在の人物であるというものです。「ノマドランド」を例にとると、作中にはノマド(車上生活者)としてリンダとスワンキーという二人のキャラクターが登場しますが、これはどちらもリンダ、スワンキーという実在の人物が本人役として演じています。また「ザ・ライダー」では落馬負傷したカウボーイのブレイディ・ブラックバーンというキャラクターが主人公として描かれますが、これを演じているのはブレイディ・ジャンドローという実在のカウボーイであり、作品自体がブレイディ自身のエピソードに基づいて作られています。ブレイディ・ブラックバーンの家族として登場する父と妹も、ブレイディ・ジャンドローの本当の家族です。このように、クロエ・ジャオは実在の人物をそのまま俳優として起用し、人物そのままのキャラクターとして登場させるという非常に珍しい手法を用いています。ここではこの手法を、仮に「クロエ・ジャオ方式」と呼称しますが、これは本人が本人役で出るという点でドキュメンタリーに近いものであると言えるでしょう。
しかしながら、ここで一つ注意しなければならない点があります。それは、彼女の作品にはれっきとした虚構の脚本が存在するという点です。「ノマドランド」のスワンキーは作中で死亡しますが、実在のスワンキーは死んでいません。ここがクロエ・ジャオ方式の面白い点です。クロエ・ジャオ方式がドキュメンタリーと呼べるかについては意見の分かれるところであり、私自身も明確な答えを出せているわけではありませんが、彼女がこの手法を用いる理由は、やはり徹底的にリアリズムを追求しているからだと考えます。ある対象、あるテーマを強い説得力を持って描く。そのためには、やはりリアリズム、すなわち現実味が必要です。であるならば、作中に現実をぶち込んでしまえば手っ取り早く済むわけです。「デューン 砂の惑星」の撮影をワディ・ラム砂漠で行うように、落馬負傷したカウボーイ役には落馬負傷したカウボーイを起用すればいいし、それを心配する家族の役には本人の家族を使えばいいと、そういう理屈ですね。しかし現実に頼ってばかりではテーマに最適化された筋道は作りづらいと思われます。そこで虚構の出番です。脚本と撮影と編集によって、現実という素材を配置・加工・成形し、テーマを体現した一つの作品を作り上げる。それこそがクロエ・ジャオ方式の用いる意味であると思います。私は彼女の作品を、リアルよりもリアリティがあるという風に評価しているのですが、それは現実と虚構を巧みな配合で掛け合わせることによって極度に純化されたテーマの結晶に触れることができるからだと考えます。
ではそこで描かれるテーマとは何か、ということですが、私は「ある個人の抱える痛みや喪失」、及び「それに対する向き合い方」であると解釈しています。「ザ・ライダー」は前述のとおり落馬負傷したカウボーイの物語ですが、そこでは「カウボーイなのに馬に乗ることができない」という大きな絶望が描かれています。また「ノマドランド」では、リーマンショックによって車上生活を余儀なくされたノマドたちという社会問題よりも、そのノマドとして生きる中での別れや喪失の悲しみといった個人的な問題が強く押し出されているように感じました。日本語字幕未対応のためまだ見てはいないのですが、長編一作目の「Songs My Brother Taught Me」もあらすじを読む限りそういった類の話ではないかと思われます。このように、クロエ・ジャオが描いている問題やテーマというのは個人の内面に関するものであり、それをその悩みを抱える本人が演じているため、そりゃあもうとんでもなく個人的で内省的な物語になるわけです。しかしながら、その問題というのは「夢を諦めるかどうか」や、「別れや喪失をどう受け入れるか」といった人類に普遍的なものであり、それを極限のリアリティで描き切る彼女の作品は、確かな説得力を持って我々の心を揺さぶります。私は「ノマドランド」には人生の答えが詰まっている作品だと思っていますが、その理由は以上の通りです。余談ですが、現在最新作にあたる「エターナルズ」はマーベルのアクション映画であり、クロエ・ジャオ方式はとられていません。さらには前三作にあった個人的問題と向き合うというテーマ性もないため、彼女のフィルモグラフィーの中では異質な感じがします。ぶっちゃけたことを言うと、私はこの作品を凡作だと評価しています。クロエ・ジャオ自身はアメコミ好きのようですが、どうもエンタメ路線では成功しなかったようです。
さて、次に映像面でのリアリティについて述べていこうと思います。といっても私はそこまで映像関係に明るくはないので専門的な解説ができるわけではありませんが、そこについてはご容赦ください。クロエ・ジャオの映像の特徴は、圧倒的な風景描写とアメリカらしさの二点であると考えます。まず風景描写についてですが、これに関しては見た方が早いとしか言えません。「ノマドランド」を見たことのある方は分かるかと思いますが、クロエ・ジャオ作品にはとにかく風景がよく出ます。多くは自然のど真ん中で、マジックアワーの感傷的な空が雄大に映し出されていて、さらにやたらとアメリカ西部です。ちょっと風景入れすぎなところはあるのですが、毎度毎度息を呑むような美しいショットになっているため飽きることはまずないです。動画的なショットの上手さかと言われると微妙ですが、少なくとも写真家の才能が抜群なのは間違いありません。
続いてはアメリカらしさについてですが、こちらの方が本題です。クロエ・ジャオの映像に、私は恐ろしいほどにアメリカらしさを感じます。アメリカらしさを煮詰めて結晶化させたものをぎゅっと固めておにぎりにしたような、そんな映像です。アメリカという国は広いですから、一概にアメリカらしさといっても色々あるわけですが、彼女の映像にはアメリカという国に普遍的な特徴がこれでもかというほど詰まっているように感じます。それは例えば西部の荒野やだだっ広い駐車場だったり、巨大なアマゾン配送センターや何の変哲もないスーパーだったりと様々ですが、フィルムの至る所から形容しがたいアメリカらしさを感じるのです。思うに、クロエ・ジャオはそうしたアメリカという国独特の空気感に対する嗅覚が非常に鋭敏なのでしょう。というのも、彼女は十五歳までを北京で過ごした紛れもない中国人であり、アメリカの文化に焦がれて国を出た、いわばアメリカかぶれなのです。よく外国人の方が日本人より日本らしさを理解している、という表現が使われますが、これも同じことなのでしょう。対象の価値や特徴は異なる対象との比較によって見えてくるものです。クロエ・ジャオについても、アメリカという国の外に立った視点を持っていたことで、下手なアメリカ人が撮るよりもいっそうアメリカらしさの詰まった映像を作れたのではないかと思われます。
かのポン・ジュノ監督は二〇二〇年代に注目すべき監督の一人としてクロエ・ジャオを挙げています。これは「ノマドランド」が公開される前の発言であり、実際その後アカデミー作品賞と金獅子賞を受賞したわけですから、その慧眼には驚かされます。また「ノマドランド」の主演であるフランシス・マクドーマンドは「ザ・ライダー」を見てクロエ・ジャオを監督に起用することを決めたようです。ポン・ジュノにしろマクドーマンドにしろ、やはりクロエ・ジャオ方式の持つリアリズムに早くから才能と価値を見出していたわけですね。最新作の「エターナルズ」は残念ながら失敗作と言える出来になってしまいましたが、彼女のキャリアはまだ始まったばかりですから、次回作が楽しみな監督であることに変わりはありません。この記事を読んでクロエ・ジャオに興味を持っていただけた方は、どうぞ「ノマドランド」から鑑賞することをお勧めします。北大映研の部室でも見ることができますので、どうぞお気軽にお立ち寄りください。ここまで長々と付き合っていただきありがとうございました。次の記事も是非お楽しみください。
北海道大学2025年度入学の皆さま、ご入学おめでとうございます。
さてもうすぐ部活・サークル選びが始まりますね。
映画が好き、映画を撮りたい!という方、大歓迎です!ぜひ一度新入生歓迎上映会にお越しください。詳しい日時は公式X(旧Twitter)(@hucinema / 北大映画研究会(北大映研))で発信していますので、確認してみてください。DM等での質問も随時受け付けています!
来週からは本HPで現役映画研究会部員による「映画ブログリレー」も始まります!
おすすめの映画や撮影の裏話などを更新していく予定ですので、こちらもチェックして入部をご検討ください。
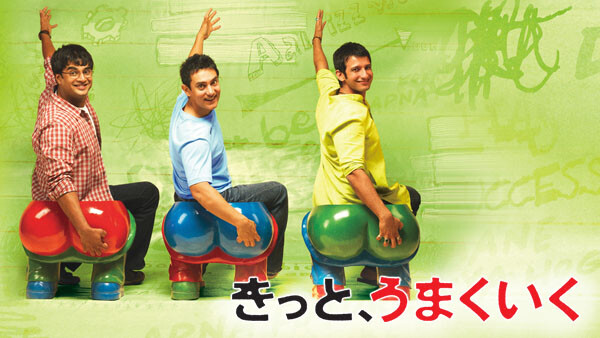 映研一年の藤田です。
映研一年の藤田です。
『きっとうまくいく』は、人生における挫折や困難を乗り越えて成長する姿を描いた感動的な作品です。主人公の若者が抱える悩みや不安、そしてそれに立ち向かう姿を映し出した映画です。
この映画では、人間関係や自己肯定感、将来への不安など、現代の若者が抱えるさまざまな問題がリアルに描かれています。その中で主人公が自らの心の葛藤から立ち上がり、前向きに行動していく姿は、観る者に希望を与えてくれます。
また、登場人物たちの成長や変化が丁寧に描かれており、彼らが失敗や挫折を経験しながらも、それを乗り越える過程で成熟していく姿が描かれています。
さらに、映像面でも繊細な演出や美しい映像が印象的です。音楽とのマッチングも絶妙で、観る者の感情を引き立てる役割を果たしています。
『きっとうまくいく』は、若者だけでなく、どんな世代の観客にも共感を呼び起こすメッセージ性の高い作品だと言えます。人間の成長や成熟、そして希望や勇気について考えさせられる映画として、多くの方におすすめしたい作品です。
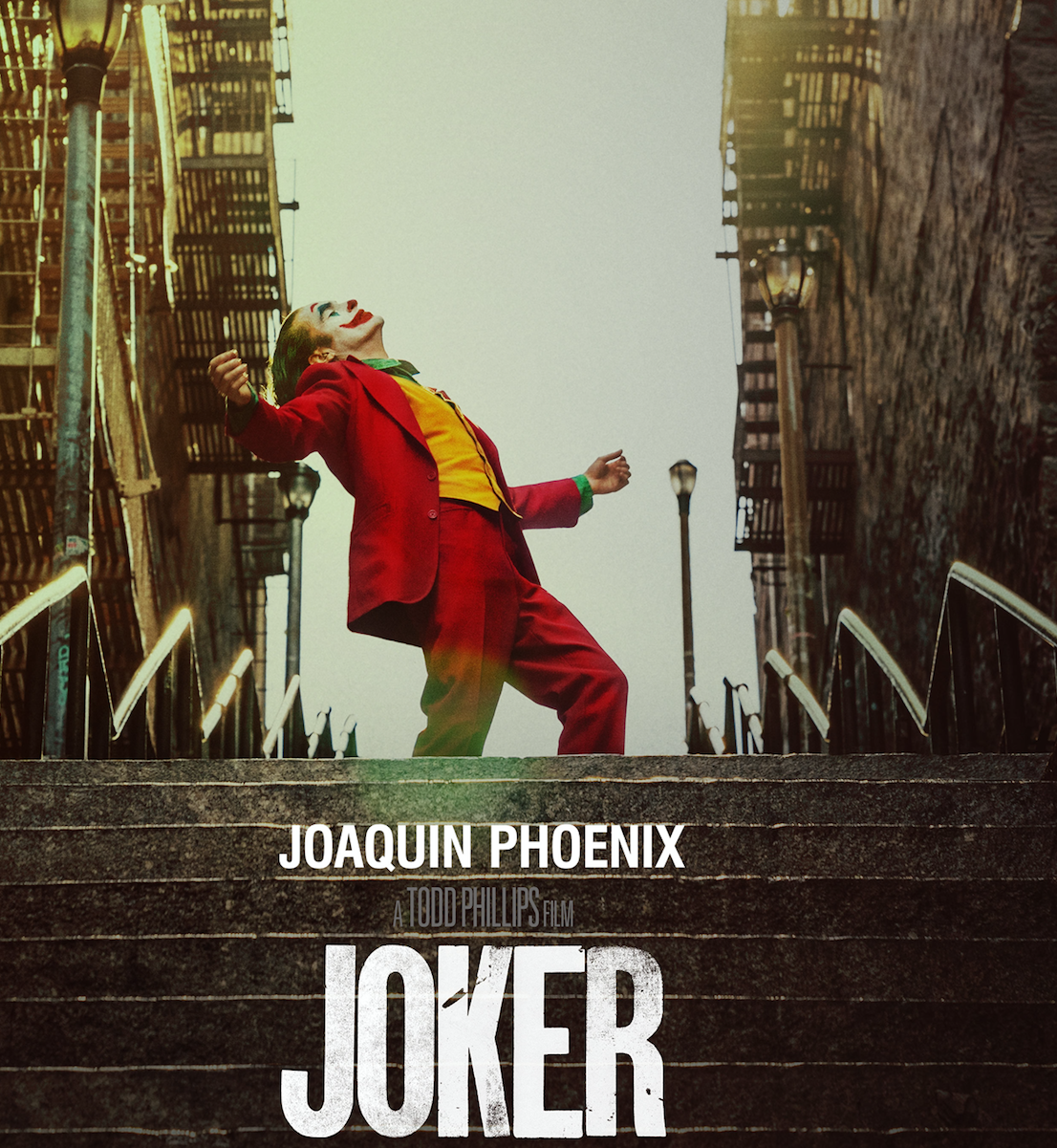 映画研究会1年の三上朔弥です。
映画研究会1年の三上朔弥です。
映画「ジョーカー」は、観客の感情を揺さぶる驚くべき作品です。主人公アーサーの内面の葛藤や孤独、狂気が描かれ、その過程で彼の心の闇に触れることができます。アーサーがジョーカーとしての変貌を遂げる過程は、観る者に深い感銘を与えるでしょう。彼の演技は見事であり、彼が抱える苦悩や絶望、怒りを痛切に感じることができます。また、ストーリーの展開には予測不能な展開があり、観る者を緊張感に包み込みます。その中で描かれる社会の偏見や差別、孤独といったテーマは、今日の現実社会にも通じる深いメッセージを持っています。暴力的なシーンや暗い雰囲気もありますが、それが作品の世界観をより際立たせています。観終わった後もアーサーの姿や心情が忘れられず、感情が揺さぶられること間違いありません。映画「ジョーカー」は、ただのエンターテインメントにとどまらず、深い人間の心理や社会問題に対する考察を促す作品として、多くの人々に強烈な印象を残すことでしょう。是非、心を震わせるこの作品をご覧になってみてください。
 工学部三年の篠原と申します。
工学部三年の篠原と申します。
突然ですが、皆さんは普段どのような映画を見ていますか?SF、サスペンス、アクション、恋愛など様々なジャンルがありますが、私は静かなSFが大好きです。「アフターヤン」や「メッセージ」、アンドレイ・タルコフスキーの「ストーカー」など。未知との静かな対面は緊張感があり、ロマンがあります。そして決まって映像が美しいのです。メッセージに出てくるエイリアンなんてもう最高。泣けてきます。他にも頭のネジがぶっ飛んだ派手な映画も好きです。「π」や「ベイビーわるきゅーれ」、「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド」などなど。そんな私が今回紹介する映画は「海よりもまだ深く」です。
なんで?と不思議に思ったことでしょう。これはホームドラマですから、地味でとっても現実的なお話しです。先ほど述べた作品群と全く系統が違います。では、なぜこの作品を紹介するのかというと、私に新しい映画の魅力を教えてくれた思い入れのある作品だからです。
これは是枝裕和監督の作品で2016年に公開されました。母親との思い出から作られた作品で、自身が9歳から28歳まで住んでいた団地で撮影されました。阿部寛を主演に迎え、母親役を樹木希林が演じます。是枝作品の名コンビですね。
実を言うとストーリーは面白くないです。主人公は金も才能もないバツイチの元小説家、母親の住む団地に偶然集まった元家族との、台風が過ぎるまでのひと晩を描いたなんのオチもないお話し。“こんなはずで無かった”という思いを持つ大人がたくさん出てきます。当時中学生だった私は、大人ってそんなものなのかと、寂しいものだなと思いました(笑)。大学生になり大人の仲間入りをしましたが未だに、こんなはずの‘こんな’も思い描けていので焦っています。地味な作品ではありますが退屈することはなく、フッと笑えるところがある良作です。
さて、私が気づいた新しい映画の魅力とはなんでしょう。それは、ただの日常も映画の手にかかればとっても印象的なものに映ると言うことです。映画ってすごい。金も才能もないバツイチのダメ男が映画の登場人物になれば、なんだか憎めないやつに見えてしまうのです。汚い風呂場も部屋の小物も懐かしいような、ずっと残っていて欲しいと思うような、味わいのあるものになります。当時の私は本作に出てきたものに憧れてたくさん真似をしました。大通駅の立ち食い蕎麦屋でサラリーマンと肩を並べて蕎麦を啜ったり、カルピス氷を作って食べたり。大きな団子は大通りの三越に売っています。さらに、ばんえい競馬を見たり(普通の競馬を見てみたい)、わざわざ墨をすってみたりもしました。まだできていないのは台風の夜に公園でお菓子を食べることですね。北海道は台風が少なくて残念です。主人公が気に入った言葉を付箋に書いて書き留めているのですが、それも真似していました。こんな普通のことが、映画になると憧れるくらい素敵なものに見えるから不思議です。となると、なんだか自分でも映画が撮れる気がしてきませんか。変に脚色しなくても日常を切り取るだけでそれなりの絵になるくらい、私たちの生活は彩りのあるもののように思えてきます。そんなことに気づかせてくれた本作は私の中で大切な映画の一つになりました。
映画に求めるものは、興奮と映像美。巨大ロボット、狂人に天才、宇宙に砂漠、超絶美人!日常には現れない存在に憧れ、現実には起こらないハプニングにワクワクする。ダイナミックな感情の駆動こそが、映画を観る醍醐味である!そして、私たちの日常は映画にも劣らぬほど味わいのあるものなのだ!
「300円くじは絶対に当たるだよ。」と言うセリフが出てきますが、この映画は私にとって当たりの宝くじだったのかもしれません。
皆さんも、たまにはほのぼの日常ムービを観てみてはいかがでしょうか。UNEXTでは無料で観られますよ。
読んでいただきありがとうございました。
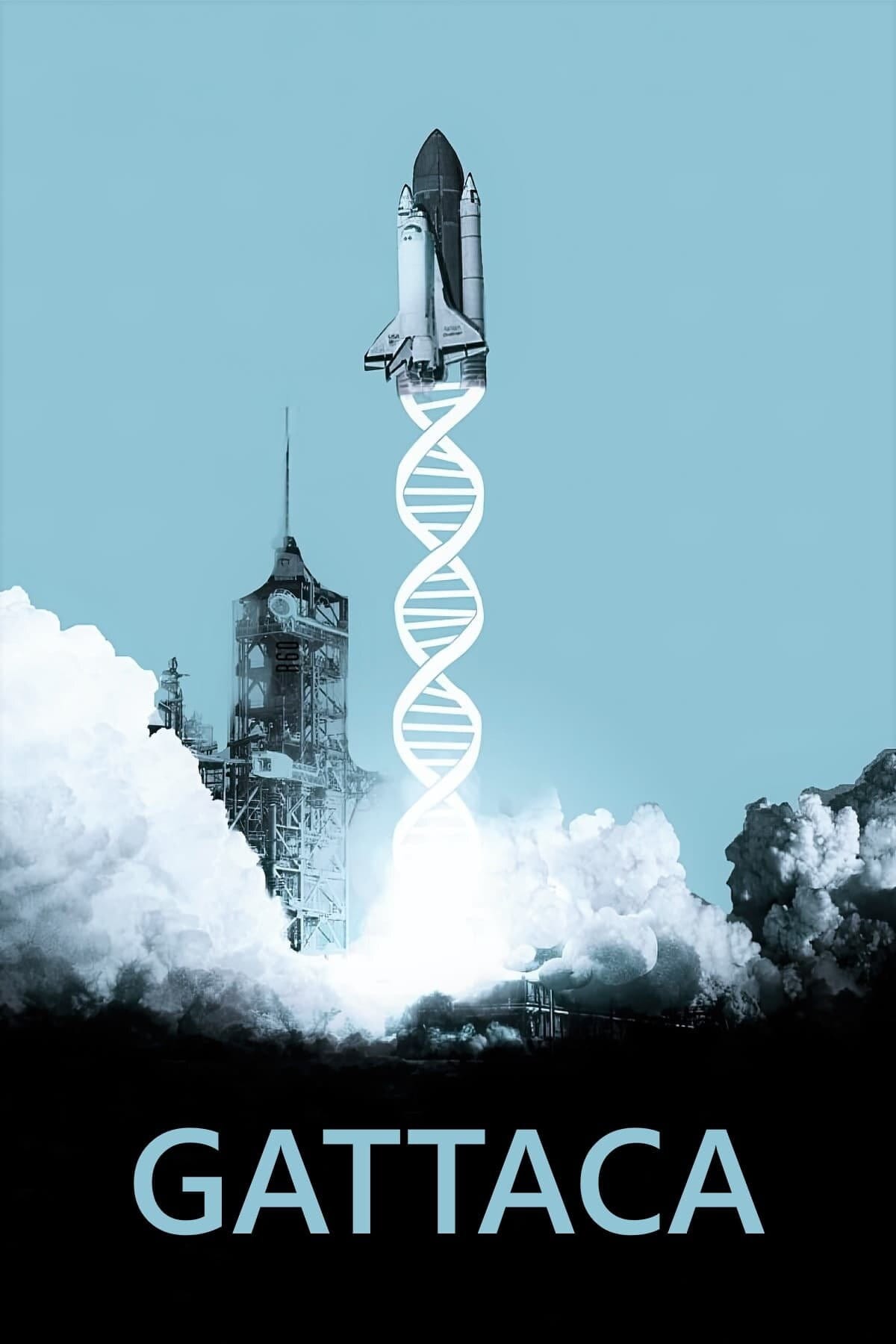
はじめまして。映研1年の古谷です。初のブログの題材は私が最も好きな映画、アンドリュー・ニコル監督作「GATTACA」(1997年・アメリカ)です。本作を鑑賞するまで、私の映画体験の中ではスターウォーズが王者に君臨していたわけですが、あっさりと一位を塗り替えたのがGATTACAだった訳です。
舞台は遺伝子操作が普通になった社会。「不適正者(自然出生児)」である主人公ヴィンセントは弟をはじめ「適正者(遺伝子操作済み児)」に常に遅れをとっています。両親の愛も肉体的能力も欠いていたヴィンセントは、宇宙飛行士になるべく努力を重ねますが、どれだけ優秀でも遺伝子検査で不適正者とわかれば落とされる無慈悲な社会でした。そこでDNAを偽装すべく、DNAブローカーを介して会った生粋の適正者ジェロームと共に、壮絶で隠匿された戦いを始めていく……詳しくは2023年の新歓ブログリレーをご覧ください。中嶋先輩が鮮やかに紹介してくれています。私の筆致では及びません。
代わりと言っては何ですが、個人的な感想を述べることとしましょう。
私にとっては幸いな事に、小学生あたりで最初に本作を鑑賞したときにはイーサン・ホークもユマ・サーマンも知りませんでした(ジュード・ロウは流石に知ってはいましたが)。これにより映画の中の描写は、当時の私にとって非常にリアルに映りました。これから行き着く社会にヴィンセントが居ておかしくない、と感じたわけです。その感覚が、この映画最大の魅力を引き出したと思います。魅力というのは「『不適正者』ヴィンセントの視点からみるからこそ感じる息の詰まる空気感」だと思います。ディストピア映画として見られることも多い本作ですが、決して「適正者」の側から見てそうであるわけではありません。ヴィンセントの弟が、適正者である自分が不適正者である兄に負けたことを「衝撃」として受け止めたように、適正者からみれば自分たちが勝っているのは当然であり、「ああ素晴らしき哉、人生」なわけです。この「もし自分が恵まれた側だったら気づきもしなかっただろう視点」を意識した時、この映画で一番の薄ら寒さを感じるのです。
非常に残酷な点として、作中で描写がありますように、ヴィンセントは「自然なままに生まれてきてほしい」という信念をもった両親の意向に依り不適正児として生まれてきています。つまり選択の余地があったわけです。現にヴィンセントが他の適正児に後れを取ったのを見た両親は、弟を遺伝子操作して出産することを決めました。選択肢があるからこそ、その責任が圧し掛かりこの映画の閉塞感に一役買っていることは言うまでもないでしょう。ただ、我が子の行く末を少なくとも成功の方向に導ける(もちろん失敗があることは描写されていますが)ことは、きっと多くの人にとっては“ユートピア”なのではないでしょうか。
非常に残念なことに、今の社会はこの表面的な“ユートピア”の方向に向かっています。ディストピアをディストピアとして認識できないままにユートピアと捉えてしまう私たちへの警鐘だ、と最初に見た時に感じた記憶があります。出生前診断も広がってきました、ネットを開けば優生思想が席巻しています。いつでも傍において見返したい作品である所以はこういう社会だからかもしれません。
作中では、事故で選手生命を絶たれた適正者ジェロームの協力のもと、ヴィンセントはDNAの偽装を図ります。ネタバレは避けますが、それでも結局肉体をどうこうできるわけではないのです。禁忌としての遺伝子操作、取り返しのつかない遺伝子操作、それとヴィンセントのアナログな対抗を対比して見ると、監督が警告を発したかったのは「人間ごときが手を出しては、取り返しのつかない一線」をやすやすと超えたくせに都合が悪くなってあがく人間像なのかな、と考えたりします。
最後に監督のアンドリュー・ニコルは素晴らしい作品を他にも製作していることをお伝えしておきましょう。名作と名高い「トゥルーマンショー」やスピルバーグが監督・トムハンクス主演の一品「ターミナル」、時間が通貨となるという点でGATTACAと同様にディストピアが描かれる「TIME」等……
とにかく、未鑑賞の方は「GATTACA」をぜひご覧ください。稚拙な長文をお読みいただきありがとうございました。
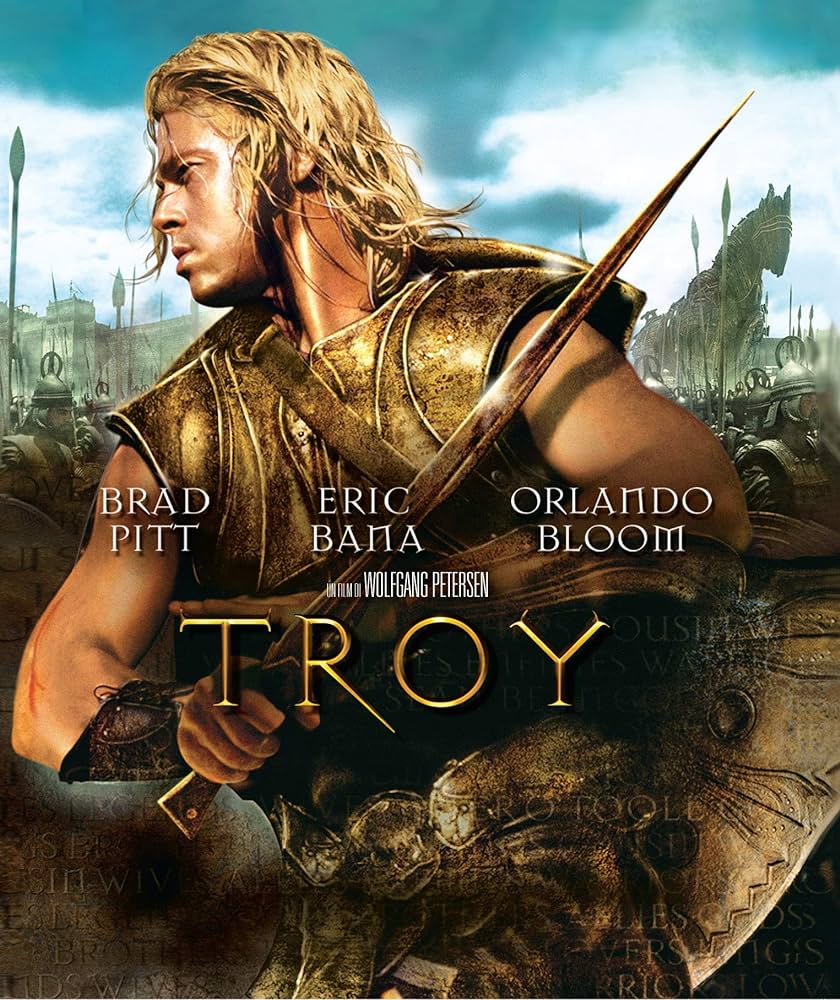 映研2年の安住です。
映研2年の安住です。
今回私が紹介する映画は、ブラッド・ピット主演の歴史フィクション映画、『トロイ』です。
タイトルの通り、この映画は、古代ギリシア最高の文学作品であるホメロスの叙事詩『イリアス』を実写映画化した作品になっています。(「イリアス」はギリシア語でトロイを意味します)
なんだかお堅そうな雰囲気ですが、物語自体は至ってシンプル。遥かなる古代に起こったミュケナイ率いる全ギリシアとトロイア王国との全面戦争を描いた、恋あり悲劇ありスペクタクルありの一国興亡史です。
全ヨーロッパ人の心の故郷ともいわれるこの偉大な古典を満を辞して映像化したのは、ウォルフガング・ピーターゼン。『エアフォース・ワン』の監督で、『イリアス』の大ファンらしいです。
さらにはキャスト陣も恐ろしく豪華です。主人公の英雄アキレスはブラッド・ピット、戦争の引き金となるトロイアの愚かな王子にはオーランド・プルーム、彼と恋に落ちるスパルタの王妃にはダイアン・クルーガー、ギリシアの賢王オデュッセウスにはショーン・ビーンが配されています。すごい!
簡単なあらすじをもう一度おさらいすると、時は古代のエーゲ海周辺にさかのぼります。アジア側の大国・トロイアとギリシア諸国家との長きにわたる戦争はようやく終結し、両陣営の間には和平が結ばれようとしていました。しかし、トロイア第二王子・パリスはあろうことかスパルタの王妃・ヘレンを駆け落ち同然に祖国へ連れて来てしまいます。これに激怒したスパルタ王は兄のギリシア盟主・ミュケナイ王に頼り、他のギリシア国家をも従えてトロイアに宣戦布告。かくして和平は消滅し、古代地中海世界をゆるがす大戦争が始まってしまう…というストーリーです。
さて、ここまでけっこう肯定的に基本情報を紹介してきましたが、実はこの映画は結構賛否の分かれている作品でもあります。
その最大の理由のひとつが、登場人物がすべてただの人間として描かれているということ。
本来原作である叙事詩は神々と人間との関わりあいを描いた神話文学であり、その世界観が古典ギリシアの人々の精神文化の支柱となっていることからも、見逃せない改変だとする批判の声が少なからぬ数挙がりました。
さらに、かといって歴史映画として観ることもかなり難しいというまあまあ厳しめな現実も存在しています。
この叙事詩は、いわゆる「エーゲ文明」時代に実際に起こった戦争をモチーフとしていることが確実視されていますが、あくまで大幅に神話的な脚色が施されいる「文学」であるため、大げさにも史書とは呼べません。
そのため、その神話文学を生身の人間を使って実際の歴史っぽく描いちゃった本作は、神話でも歴史でもないという微妙な立場に置かれることが運命付けられていたのです。
しかし、こうした声を聞いてもなお、私はこの作品に強く魅了され続けています。
いくつか理由はありますが、その最大のひとつは、古典古代以前のエーゲ海世界が説得力のある形で描かれているという点にあります。
先述したように、『イリアス』の舞台となったのは、ホメロスの生きた時代から更に数世紀ほどさかのぼったエーゲ文明の時代です。
我々が一般に「古代ギリシア」と聞いて思い浮かべる世界とは大きな時間と文化の隔たりがあるため、アジア/オリエント諸文明の影響を強烈に受けたヨーロッパ文明の黎明・始祖の姿を、これでもかというほどつぶさに目に焼き付けることができます。
もちろん映画的な脚色・想像は各所に入っていますが、考古学の発展にも依拠して、この映画の劇中美術には強い考証的こだわりが垣間見えます。
たとえば劇中では何度も葬儀のシーンが登場しますが、やたらアジアンな礼装をまとった王族たちが見守るなかで金属貨幣みたいなのを遺体の両目に置く風習には、「異文化っぽいな〜」とつぶやいてしまうこと請け合いです。
また、この作品においては何より人物ひとりひとりの魅力が強く感じられます。
神性を剥奪された英雄たちは、代わりに観客の強い共感を生む原動力となる脆くて曖昧な人間性を手にしました。
その筆頭は、やはり主人公のアキレスです。
原始的なマッチョイズムを体現したような肉体的強さを持つ女たらしの色男ながらも、どことない危うさをはらんだ目つきや、心の奥に抱えこまれた寂しさをふとした瞬間にもらす様子などからは、彼の人間的な不完全性が読み取れます。
また、なにより忘れられない存在としては、トロイア現王のプリアモスがいます。
彼自身は比較的温厚かつ寛大な性格で、善王の部類に属する王様であることは誰の目にも明らかです。しかしその穏和な性格もあってか醜態を晒した息子を見捨てることができず、苦渋の尻ぬぐいとして開戦を余儀なくされたことは不憫にさえ思えてきます。
ですが、そのように自己の主張が控えめな老王が、劇中のあるシーンにおいては完全なる独断によって非常に危険な賭けともいえる行動へその身を委ねます。
戦時の国家運営とはあんまり関わりのない私情もいいところな理由ではあるのですが、何しろその行動とは、憎むべき仇敵のもとへ赴き、その足へ口づけをしてまで愛する者の亡骸を取り戻そうとするという危険極まりないものです。私はここから彼の底知れぬ人格の一面を見せつけられたような感覚が芽生え、畏怖に近い感情すら覚えてしまいました。
明日の存在すら定かではないたそがれの大国において、死んでしまった家族を正式な形で弔ってみせようという固い意志には、戦争により一時的に消失・忘却の対象とされてしまった人間性、すなわち生活の回復への強い想いが見てとれるように思えました。
それゆえ、燃え盛るトロイアの街を彼が見つめるシーンには、他に替えようもないほどの強い悲しみが宿っているように感じられるのです。
そして劇中屈指の愚か者と言える王子・パリスは、一方で最も魅力に溢れたキャラクターとも言えます。
色魔でありながら幼稚で暗愚、おまけに臆病という人格のどうしようもない面ばかり見せつけられますが、物語の後半では自己の成長に向かって懸命にもがく姿も描かれることから、観客は彼のことを完全に嫌いになることができないのです。
彼はおそらく理想主義者で、事の重大さを十分に理解しきってはいません。しかし、彼が自身の迂闊さと未熟さを少しずつ噛み締めた末に物語のクライマックスで象徴的な一矢を放つ描写には、私はある種の消極的な人間讃歌のようなものを感じました。
この映画が描くものは、文字通りきわめて古典的な国家の存亡を賭けた戦史であり、典型的な悲恋であり、あまりにも象徴的にすぎる復讐劇です。
また、統治者の私情により国家の趨勢が大きく揺るがされる未成熟の政治機構、儀礼的で非生産的な決闘、なすすべもなく陥落する市街のなかで死に絶える無数の人々の描写など、物語の構造・内容ともにこの作品はシンプルな叙事詩の枠組みを出ることはありません。
しかし、そうした形式の制約があるからこそ、キャラクターの心のはたらきの機微や人間的精神の普遍性をいっそう強い形でそこかしこに読み取ることができるように思われます。
何千年も昔の架空の人間たちの物語がさまざまな角度から我々の胸を打つのは、そこに確かに繊細かつ複雑な人間像の構築がなされていることに他ならないように感じられてなりません。
そのため、原作とは大きく異なった内容ではありますが、ある意味ではこれは真に古典古代の精神を受け継ぐ人文主義的作品なのではないか…?とさえ思わされました。(なんら深い省察を経ていない考えですので、間違っていたらすみません。)
こういった理由から私は、やはりこの作品に強い魅力を感じてしまいます。
あとは、アキレスとヘクトル(パリスの兄・トロイア第一王子)の決闘シーンがめっちゃかっこいいです。そこだけでも観てほしいです。
たくさん書いてしまいましたが、結構ロマンがあって面白いので歴史好きの方はぜひ一度観てください。そうじゃない人も観てみてください。北図書にもあったはずです。