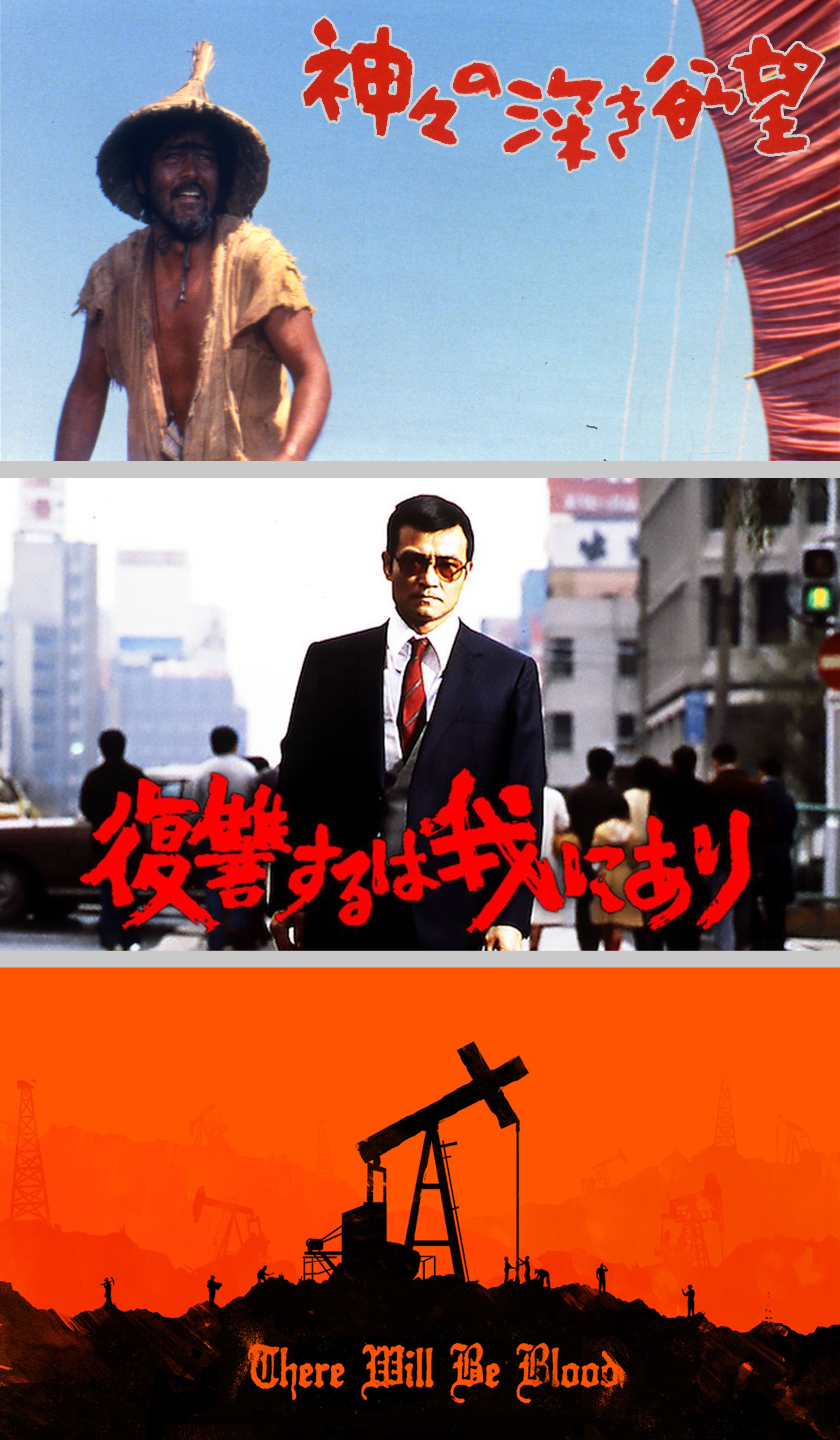 映研3年目の中嶋です。僕は前回の記事(https://
映研3年目の中嶋です。僕は前回の記事(https://(
『神々の深き欲望』(1968年)
この映画の舞台となるのはクラゲ島と呼ばれる南の島です。
主人公である太根吉はその信仰に基づいて差別されており、
そんな島にも文明的な施設があります。小さな製糖工場です。
この映画は邦画史に残るレベルの大傑作(
『復讐するは我にあり』(1979)
主人公榎津巌はエゴイストの権化のような男です。
この映画は実際に起こった事件を基にしており、
『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』(2008年)
この映画は2008年公開のアメリカ映画です。監督はポール・
舞台は19世紀から20世紀にかけてのアメリカ、
事業拡大のためアメリカ各地を点々できるほど成功し、
そんな彼の元に、ポール・
しかし、事業はスムーズには進みません。
順風満帆に進んでいき、
この教会は「教会が信仰心を広めたため、村が豊かになった。」
というあらすじだと僕は解釈しています。なぜあらすじに解釈?
例えばポール・サンデーと名乗った男とイーライ・
その為、観ている情報をどう判断するかは観客に委ねられており、
僕はこの三本の映画を勝手に三部作と考えて観ています。
*おすすめの観る順番は『神々の深き欲望』、『ゼア・
